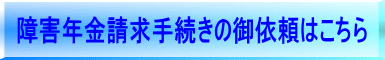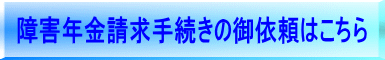障害年金の額は?
障害基礎年金の額=国民年金から支給されます。
下記の金額は令和6年度の金額です。
●障害基礎年金1級:1,020,000円
●障害基礎年金2級: 816,000円
※下記の場合で、障害基礎年金2級又は障害基礎年金1級に該当する場合は、子の加算額が追加されて支給されます。
- 障害基礎年金受給者により生計維持されている「18歳になった後の最初の3月31日までの子が居る場合
または - 障害基礎年金受給者により生計維持されている「20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子」が居る場合
![[heart]](image/face/heart.png) 例
例
- 1級=1,020,000円+子1人目234,800円+子2人目234,800円 3人目以降78,300円
- 2級=816,000円+子1人目234,800円+子2人目234,800円 3人目以降78,300円
- 年金法上の子とは、「18歳到達後の最初の3月31日までの子又は20歳未満の障害等級に該当する子」のことです。
- 「18歳到達後の最初の3月31日までの子」とは、ザックリ記すと「高校を卒業する前の子」です。
- 年金法上の子とは、「18歳到達後の最初の3月31日までの子又は20歳未満の障害等級に該当する子」のことです。
障害厚生年金の額=厚生年金から支給されます。
- 1級=報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金234,800円
- 障害厚生年金受給者(1級)が「生計維持関係にある配偶者」を有する場合は配偶者加給年金額が追加されて支給されます。
- 2級=報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金234,800円
- 障害厚生年金受給者(2級)が「生計維持関係にある配偶者」を有する場合は配偶者加給年金額が追加されて支給されます。
- 3級=報酬比例部分の年金額(最低保障額=612,000円:令和6年度額)
障害厚生年金受給者(3級)が「生計維持関係にある配偶者」を有する場合には、配偶者加給年金額は支給されません。- 報酬比例部分の年金を計算をする際に、厚生年金加入期間が300月(25年)未満であれば、300月とみなして計算してくれます。要するに、年金加入期間の最低保障です。
ただし、厚生年金加入期間中に障害の原因となった傷病の初診日(○年○月○日)があることが条件です。つまり、在職中に患った傷病が原因で障害が残ってしまった場合には障害厚生年金の加入期間最低保障300ヶ月が適用されるわけです。
- 報酬比例部分の年金を計算をする際に、厚生年金加入期間が300月(25年)未満であれば、300月とみなして計算してくれます。要するに、年金加入期間の最低保障です。
障害厚生年金受給の場合の配偶者とは、下の条件をクリアーする配偶者です。
❶配偶者の年齢が65歳未満
❷配偶者が、加入期間20年以上の老齢厚生年金を受給できないとき
❸配偶者の年収が850万円未満であるとき(または配偶者の年間所得が6,555,000円未満であるとき)
❹障害年金受給者と配偶者が生計同一関係にあること
生計同一関係とは下記のようなケースです。
- 障害年金受給者と配偶者の住民票が同じ(住所が同じ)
- 障害年金受給者と配偶者の住民票が異なるが(住所は別々だが)、以下のようなケースの場合
- 日常生活を一緒に暮らし、且つ、家計を同一にしている場合
- 定期的に送金等の経済的支援が行われていること。
- メール・郵便等の相互の音信が有ること。
- 定期的に訪問していること。
- 報酬比例部分の計算につきましては、複雑ですので、ここでは省略させていただきます。
- 厚生年金被保険者(給与又は役員報酬から厚生年金保険料が控除されている人)が障害等級2級に該当した場合。
配偶者1人+子ども1人。加入月数=300月- 障害厚生年金は「660,000円/年額」とします。
生計同一の配偶者が居るので、加給年金額「234,800円」
「660,000円+234,800円=894,8000円 - 障害基礎年金=816,000円+234,800円(子の加算)
=1,050,800円/年額 - ∴障害厚生年金+障害基礎年金=894,800円+1,050,800円=1,945,600円/年額
- 1,945,6000÷12=もらえる障害年金額(月額)は「162,130円」です。)
- 障害厚生年金は「660,000円/年額」とします。
会社勤め期間中(厚生年金加入期間中)に発病しても、初診日が退職後の国民年金加入期間中だと、障害基礎年金のみを請求しなければなりません(障害厚生年金は請求できません)。裁定請求書は障害基礎年金請求のための裁定請求書(「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」)を使用します。
会社勤め期間中(厚生年金加入期間)で20歳以上65歳未満であれば、国民年金の第2号被保険者になっているので(厚生年金と国民年金の同時ダブル加入状態なので)、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を請求することができます。裁定請求書は紫色の裁定請求書を使用します。
このように、障害年金請求では初診日が非常に重要になります。
障害等級についてはこちらをクリック
- 非常におおまかな基準を下に記します。
国民年金の障害年金 厚生年金の障害年金 障害の程度 障害基礎年金1級 障害厚生年金1級 障害の程度は同じです。 障害基礎年金2級 障害厚生年金2級 障害の程度は同じです。 障害基礎年金に3級は有りません。 障害厚生年金3級
| 1級 | 自分以外の人(家族等)の援助が無ければ、ほとんど生活ができない程度の障害の状態 。入院している場合は、活動の範囲がベッド周辺のみである。家庭内であれば、活動の範囲が就床室内のみである。 |
|---|---|
| 2級 | 日常生活が著しい制限を受ける程度の障害状態。必ずしも自分以外の人(家族等)の援助は必要ないが、労働して収入を得ることができない状態。例えば、家庭内での軽食づくり・下着の洗濯等はできるが、それ以上の活動はできない状態。 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける程度の状態。 |
障害年金の額
「20歳以上65歳未満」の期間に初診日が有るケースと仮定します。
2級のケース ※あくまでも目安です。この額を保証するものではありません。
| 障害基礎年金(年) | 障害厚生年金(年) | 合計額(年) | |
|---|---|---|---|
| 平均年収250万円 | 795,000円 | 約370,000円 | 約1,165,000円 |
| 平均年収300万円 | 795,000円 | 約440,000円 | 約1,235,000円 |
| 平均年収400万円 | 795,000円 | 約590,000円 | 約1,385,000円 |
| 平均年収500万円 | 795,000円 | 約730,000円 | 約1,525,000円 |
| 平均年収600万円 | 795,000円 | 約880,000円 | 約1,675,000円 |
- 上記の額は「子無し」・「配偶者無し」として計算しました。よって上記の額には、「子の加算」と「配偶者加給年金」が含まれていません。
障害年金請求手続き代行サービス
全国対応いたします。
- 障害年金請求を決心してから実際に障害年金を受給するまでには、最低でも4か月の期間を要します。
- 当事務所とお客様との情報のやり取り・受診状況等申立書の交付手続き・申立書の作成・医師が障害年金用診断書を書く手間等にかかる期間を合計すると1.5か月~2か月
- 日本年金機構が早めに裁定してくれた場合で2か月
- よって、「障害年金受給通知」がお客様のご自宅に届くまでに、最短で3か月半程度はかかります。
- そして、実際に障害年金が振り込まれるのが「障害年金受給通知」が届いた月の翌月または翌々月です。
- ∴障害年金請求を決心してから実際に障害年金を受給するまでには、最低でも4か月はかかります。
当事務所はメンタル系の障害年金請求に絞っています。
メンタル系障害なので、面談は不要です。
- うつ病・双極性障害・統合失調症等のメンタル系の障害の場合、人と接することに負担を感じられるケースが多いです。電話で話をすることにも負担を感じられる方が少なくありません。
- 当事務所の障害年金請求手続きの場合、面談は不要です。面談の代わりに、メール相談で対応いたします。
- ただし、面談を御希望される場合には、当然、面談にも対応します。また電話相談を御希望の場合にも、当然、電話相談に対応いたします。
私(社会保険労務士・鈴木好文)が今まで障害年金請求手続き代行をしてきた中で、私と御依頼人様が一度も会うことなく障害年金を獲得したケースも有ります。ただし、面談はしなくてもメール・電話・郵便等により情報を相互にやり取りします。
また、私(社会保険労務士・鈴木好文)が御依頼人様と会うことは1回又は2回です。しかし、それでも障害年金を獲得しています。※ご希望であれば、3回以上の面談は全く構いません。
- 実は、これにはそれなりの根拠があります。それは、当事務所独自の障害年金請求方法があるからです。それを以下に説明します。
一般的な障害年金請求手続きの流れ
- 一般的には、医師により受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらった後に診断書を記入してもらいます。下の図を御覧ください。
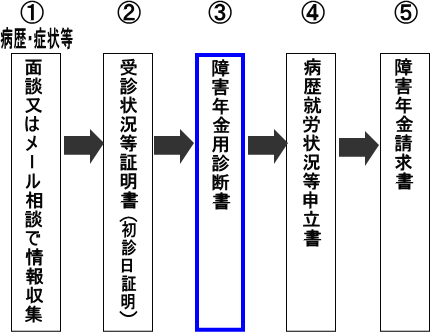
当事務所の障害年金請求手続きの流れ
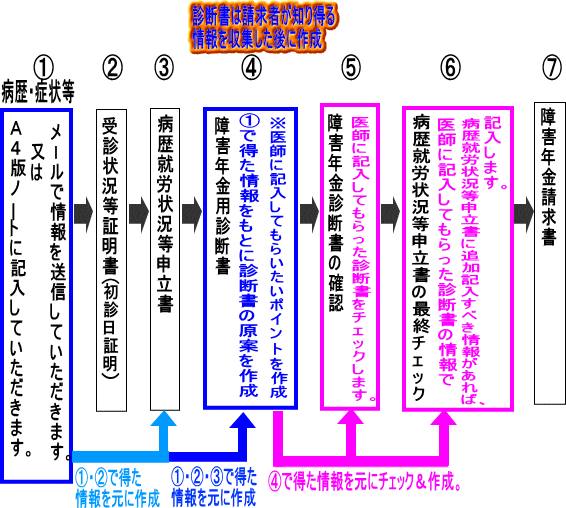
当事務所ではお客様の病歴・症状等の情報を得た後に診断書の原案を作成
- それに対して、当事務所は医師により受診状況等証明書(初診日証明)を記入してもらい、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた状態になった後、医師に診断書を記入してもらいます。
- このようにすることにより、御依頼人様からそれまで得た病状等の情報を診断書に反映させることが可能となるからです。
- 診断書は障害年金受給においては最重要の書類です。診断書の内容により障害年金がもらえるか否かが、おおよそ決まります。だから、病歴就労状況等申立書をほぼ完成させた後で医師に記入してもらうのです。
病歴就労状況等申立書は重要な書類です。
- 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
請求者が自分の病歴・症状等について主張できる書類です。
- 障害年金受給権獲得において最重要な書類は、診断書です。
しかし、病歴就労状況等申立書も重要な書類です。自分の生活状況・症状の程度等について詳しく書いてよい書類だからです。生活状況や症状の程度は障害年金の受給権を獲得するうえでは、非常に重要です。当事務所では、医師により記入してもらった診断書の情報を元に病歴就労状況等申立書で追加記入すべき内容の情報があれば、その情報を病歴就労状況等申立書に追加記入します。
つまり、病歴就労状況等申立書を複数回チェックします。
書類のやりとりは郵送により行います。
当事務所と御依頼人様との間の郵送料は全額当事務所が負担します。
- 当事務所から予め「レターパック520」をB0版の大きな封筒に入れて郵送します。御依頼人様は、同封されているレターパック520に書類を入れて当事務所まで郵送してください(切手貼付不要で、ポストに投函するだけです}。
- パソコンを使って画像を送付することも受け付けます。
病院へ同行することも可能です。=交通費のみ請求いたします。
御希望であれば、医師に診断書を記入してもらう際に同行いたします。
- 同行費用につきましては、交通費のみ請求いたします。