事後重症請求とは?
事後重症請求とは?
- 初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)には障害等級に該当していなかったが、後で障害が重くなった場合に請求する方法です。
例えば、初診日が平成30年2月1日で(「うつ病」と診断された)、その後もずっと病院に通院し、1年6ヶ月が(令和元年8月1日以降も)経過した後も病気(「うつ病」)は治癒ぜず、通院していた。しかし、会社には勤務し続けていた。だが、令和元年11月1日以降は、病気が重くなったため、令和元年11月1日以降は会社を休職し続けている状態である。
この場合、令和2年1月20日に障害年金請求関係書類を年金事務所に提出し、その後に日本年金機構の審査を受けて障害年金受給が認められた場合(障害等級に該当した場合)、令和2年2月以降の分の障害年金が受給となります。
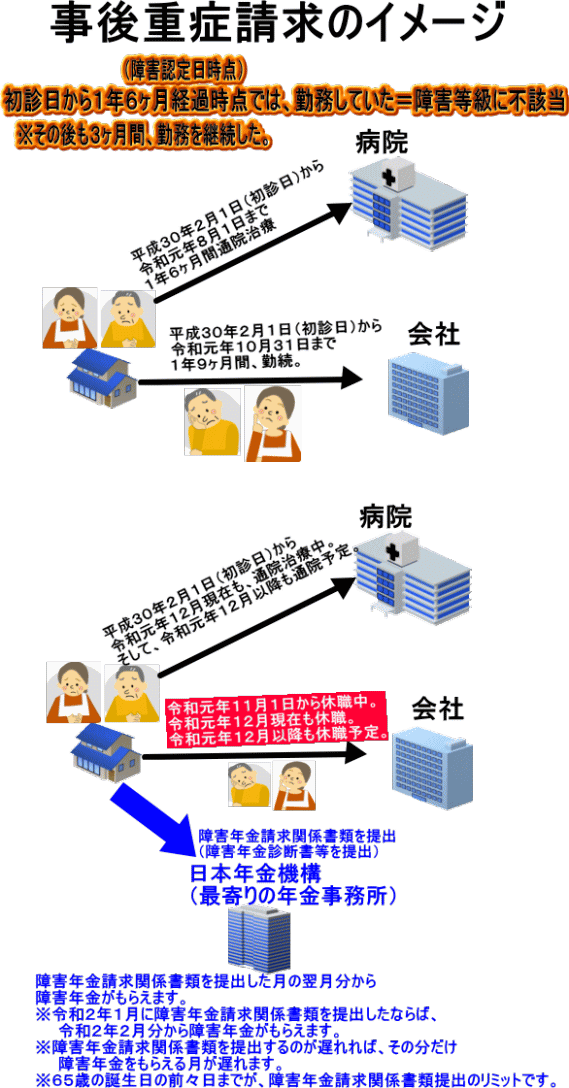
- もし、初診日から1年6か月が経過した時点で障害等級に該当する場合は、初診日から1年6か月が経過した時点での症状で障害年金を請求する方法が有ります。この請求方法を「障害認定日請求または「本来請求」と言います。
- 障害認定日請求をしても、過去の期間に遡って請求できるのは、過去5年前までです。
例えば、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日)が平成24年10月20日の場合、令和元年10月20に障害認定日請求で障害年金を請求して障害年金の受給が認定されたとしても、支払われる障害年金は「平成26年11月以降の期間分」です。つまり、「平成24年11月分から平成26年10月分まで」の2年間分の障害年金については、時効により、もらえません。
事後重症による請求は、65歳の誕生日の前々日までに書類を提出!
事後重症による請求の場合、請求月の翌月分から障害年金が貰えます。
- したがいまして、請求するのが遅れると、障害年金をもらい始める時期も遅れてしまいます。
- ただし、請求する障害年金は初診日において加入していた年金の障害年金となります。
- 事後重症による障害年金請求は、65歳の誕生日の前々日までに、必要書類を年金事務所に提出しなければなりません。
- 事後重症請求には、大きく分けて2つのタイプが有ります。
❶初診日から1年6か月経過した日後に障害が重くなったケース
初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)には障害程度が軽くて障害等級に該当しなかったが、その後に障害が悪化し、日常生活に相当の支障が出るようになり、障害年金を請求する方法です。
事後重症請求をする場合には、年金事務所で以下のものを提出します。
以下に初診日において厚生年金に加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
※現症というのは、医師が、その診断書を書いた日の症状・障害の程度等のことです。医師が現症の日付を「令和元年10月20日」と記した場合、医師は、その人の「令和元年10月20日時点での症状・障害の程度等」を障害年金用診断書に記入したということです。この場合、令和2年1月20日までに、この診断書を年金事務所に提出しなければ、この診断書は無効となります。
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
※現症というのは、医師が、その診断書を書いた日の症状・障害の程度等のことです。医師が現症の日付を「令和元年10月20日」と記した場合、医師は、その人の「令和元年10月20日時点での症状・障害の程度等」を障害年金用診断書に記入したということです。この場合、令和2年1月20日までに、この診断書を年金事務所に提出しなければ、この診断書は無効となります。
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
❷障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)の診断書が得られないケース
具体的には以下のケースです。
- 初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の診断書を書いてもらおうと医師に依頼したが、カルテが既に廃棄され、「初診日から1年6か月時点の診断書は書けません!」と医師に断られたケース
- 初診日から1年6か月経過した時点で診療を受けていた病院が、既に廃業しているケース
- 初診日から1年6か月経過した時点(障害認定日)の時点では、医師の診療行為を受けていなかったケース
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日ちょうど(ピッタリ)である必要は有りません。初診日から1年6ヶ月から1年9ヶ月以内の期間の現症の日付の障害年金診断書であれば、認定日請求ができます。
以下に初診日において厚生年金に加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
※現症というのは、医師が、その診断書を書いた日の症状・障害の程度等のことです。医師が現症の日付を「令和元年10月20日」と記した場合、医師は、その人の「令和元年10月20日時点での症状・障害の程度等」を障害年金用診断書に記入したということです。この場合、令和2年1月20日までに、この診断書を年金事務所に提出しなければ、この診断書は無効となります。
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 配偶者・高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 配偶者が居れば、配偶者の所得証明・非課税証明書(または課税証明書)等の配偶者の収入を証明するもの
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 「年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) 様式第104号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
以下に初診日において国民年金だけに加入していた場合の提出書類を記します。
- 受診状況等証明書
請求する障害年金に関する傷病についての初診日を証明したもの=医師に書いてもらいます。
- 病歴就労状況等申立書、病歴就労状況等申立書(続紙)
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
したもの - 「病歴就労状況等申立書」の記入例は下のボタンをクリック
- 1枚目
- 続紙
- 発病から障害年金請求日までの病状・日常生活の状況等を記入
- 医師が記入した診断書1枚 精神の障害用診断書はこちらをクリック
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
※現症というのは、医師が、その診断書を書いた日の症状・障害の程度等のことです。医師が現症の日付を「令和元年10月20日」と記した場合、医師は、その人の「令和元年10月20日時点での症状・障害の程度等」を障害年金用診断書に記入したということです。この場合、令和2年1月20日までに、この診断書を年金事務所に提出しなければ、この診断書は無効となります。
- 請求日以前(年金事務所に提出する日以前)3か月以内の障害状況等を医師が記したもの。請求日以前3か月以内の現症の日付の診断書
- 住民票(世帯全員が記載されているもの)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 高校生以下の子供(18歳到達後の最初の3月31日に到達していない子)が居れば(または20歳未満の障害を持った子供が居れば)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 交付された日付から障害年金請求日までの期間が1か月以内のもの
- 「年金請求書(国民年金障害基礎年金) 様式第107号」
- 年金事務所でもらえます。
- その他の書類として、身体障害者手帳のコピー・療育手帳のコピー・精神障害者保健福祉手帳のコピー等の障害を証明するもの。=必須というわけではありません。しかし、障害状態を証明するものですから、提出した方が良いです。
